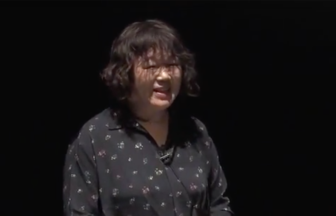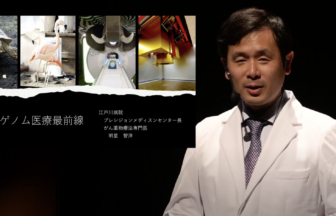- 内容:Contents
- プレゼンター:Presenter
- テキスト:Transcript
社会連携 ― 医療連携,多職種連携のその先
地域包括ケアシステムにおいては、入退院を調整する医療連携、在宅での療養・介護を支援する多職種連携に加え、住民・企業・NPO等との連携も求められています。私はこの異分野・異業種との連携を「社会連携」と呼び、研究しています。 たとえば倉敷の“わが街健康プロジェクト”では、地域医療の課題を医療者と一緒に考える市民サポーターの育成に力をいれています。新潟では医療者グループと新聞社が手を組んで健康情報の発信を始めました。山形には医療者と異業種が交流するコワーキングスペースが設置されています。 これらの事例においては、住民の意識啓発や生活支援・介護予防等サービスへの異業種の参画が意図され、様々な立場の人が、同じ目線で膝を突き合わせる関係づくりに挑戦しています。医療・介護の境界を越え、地域との“対等で近い関係”を結ぶ「社会連携」こそが、地域が一体となって包括ケア時代を迎えるための要件であると考えます。
鎌田 剛
KAMADA GO
東北公益文科大学・准教授
NPO法人あらた・理事
(ほか自治体関係の委員委嘱多数)
北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士後期課程,日本学術振興会特別研究員を経て2005年より東北公益文科大学専任講師。博士(知識科学)。2012年より准教授。2013年10月からは,文部科学省「地(知)の拠点整備事業」の担当者として,大学と地域の間に立ち地域課題の解決と人材育成の各種プロジェクトに取り組む(~2018年3月)。その一環として立ち上げた「やまがた多職種連携学生ネットワーク」では,県内外の医療・介護を学ぶ学生を巻き込んで,“学生時代から顔の見える関係を”を合言葉に,IPEの新しい形を提案した。
専門は地域医療連携,多職種連携,MEDでも紹介した医療と異分野との社会連携。これらの「連携」について,主に組織論や社会的ネットワーク論の立場から解釈を与え,実践のポイントを示す手法を用いる。近年は,次代の高齢者の暮らしのあり方を地域づくりと関連づけ,CCRCや高齢者の居場所・活躍の拠点づくりなども研究対象とし,各地の調査を進めている。またこれらの専門に関する講演や研修講師の依頼も多数引き受けている(年間30回前後)。
「各地の「連携」の成功や失敗の要因を,理論的に説明する技術を持っています。たとえば,「多職種連携がうまくいっている地域では,顔の見える関係を超えて,『一目置く関係』が育っています。事例として山形県鶴岡市で活躍するある薬剤師のケースをとりあげましょう(後略)」のように,各地の事例調査から得られたデータをもとに,成功の秘訣や失敗の教訓を理論的にあぶり出し,学会,業界誌,講演・研修などで発表しています。理論は難解なものではなく,むしろ反対に,現場の複雑な事象をシンプルに説明してくれる手がかりになります。理論研究の立場から,医療・介護の連携現場に微力ながら貢献いたします。皆さま,どうぞよろしくお願いします。」